九度山町にある2基の特異な煉瓦拱橋
|

奥に大師第16号拱渠を望む九度山発電所水路橋 |
| 九度山町は、和歌山県北東部に位置する人口3,500人余りの町である。高野山を開いた弘法大師が月に9度山を下りて町内の慈尊院に住む母を訪れたことからついた地名という。そこにある2基の特異な煉瓦拱橋をご紹介する。一般に、煉瓦で斜橋を架ける場合はねじりまんぽとするのが原則だが、本稿で扱う2橋はいずれもこれによらない点で特異なのである。 |
|
|
|
|
|
(1)大師第16号拱渠
度山町は、高野山から発する不動谷川が丹生川と合流して紀の川に注ぎ込む地点にあり、明治34(1901)年の紀和鉄道(現在のJR和歌山線)開通を契機に高野山への登山口としてにぎわった。現在は南海高野線が大阪に通じており交通は便利であるが、人口は年々減り続けている。産業としては農業が中心であり、柿で名高い。
高野山参詣の中継点であった当地に高野山への鉄道を敷設する動きが始まったのは、「高野大師鉄道」が設立された大正9(1920)年のことだった。
|
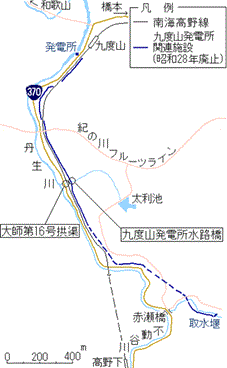 |
|
図1 大師第16号拱渠及び隣接する九度山発電所水路橋の位置 |
同社は汐見橋〜橋本間の鉄道を経営していた「大阪高野鉄道」が設立した会社で、社長に根津 嘉一郎1)を据えて建設を始めた。しかし、紀ノ川を渡ることができず、11年に大阪高野鉄道ともども「南海鉄道」に併合される。これにより工事は遅滞なく進められ、14年に九度山から現在の高野下までが開通して、難波からの直通運転が開始された。
今回 紹介する大師第16号拱渠は、九度山駅から南に900m余り進んだところにあり、南海高野線が太利(ふとり)池から流れ出る水路やそれに沿う通路と約70°の角度で交差している。交差物件に対して斜めに煉瓦拱橋を架ける場合、ねじりまんぽの技法が使われることは先に述べたが、本橋は驚くべきことに斜橋でありながら直橋と同じように水平に積んでいるという不思議な構造物である。稀な施工例だ。
これは、煉瓦構造物の理論では脆弱な構造と言わざるを得ない。すなわち、理論では煉瓦と煉瓦の間では圧縮力しか伝達しないことが仮定されており、斜橋において煉瓦を水平に積んだのでは橋梁の全幅員において伝達できないので斜めに積むのがねじりまんぽである。
|
 |
|
図2 斜橋でありながら直橋のように煉瓦を水平に積む大師第16号拱渠 |
が、実際には目地のモルタルによって煉瓦はある程度は一体化されている。よって、本橋が成立しているのだと言える。
考文献1によれば、当時はねじりまんぽの設計について、投影図を描いたり展開図を作成するなどの図学的設計法がいくつか存在していた。ねじりまんぽに関する外国の文献を毛利
重輔と伊藤 鏗太郎が翻案した「斜架拱」(明治32(1899)年刊行)では、三角関数を使った計算式を27も掲げる一方、これは当時の技術者の数学的知識や計算技術からかなり困難であろうとの考慮からか、併せて「バアロー」氏のノモグラムによる図解法を例題付きで解説している。また、松永 工、飯田
耕一郎の共著になる「アーチ設計法」(1907(明治40)年刊行)では、螺旋式、対数曲線式、カウスホーム式(Cow's Horm Method)の3種類の設計法が掲げられている。
ただし、当時の図解法により得られた値は解析的に求められる理論値と比べて多少の誤差を含んでいたようだ。交差角が約70°である本橋の場合、ねじりまんぽにした時の煉瓦の傾きは13°ほどになるはずである。設計者は、目地の効果を見込めばこれを0としても誤差の範囲内だと判断したのだろう。この判断は理論より危険側にあるため、この方法での建設を決意するためには、目地によりどの程度の一体化が期待できるのかを確かめておく必要があると思われる。しかし、管理者である南海電鉄によれば設計・施工段階の資料は残っていないそうで、どのような検討を行ったかは不明だ。
よって、ここからは筆者の想像である。本橋が架けられた大正時代には、関西を中心に30基ほどのねじりまんぽがすでに供用されていた。これらを観察した技術者の中には、煉瓦の傾きにばらつきがあることに気づいた者もあったのではないか。事実、煉瓦の傾きの理論値と実測値の比較が参考文献1に掲載されており、これによれば実測値が理論値とほぼ一致しているものがある一方、実測値が20°近くも大きいものもあるようだ。
|
 |
|
図3 アーチ部のみ煉瓦の端面がそろっていない |
また、明治の半ばからガウス(F. G. Gauss)が作成した対数表や三角関数表がわが国でも紹介されており、これに接した技術者には「斜架拱」に示された式で解析的に解を得ることが可能であったかも知れない。明治時代に図解法で設計・架設されたねじりまんぽが煉瓦の傾斜に誤差を有していても問題なく供用されていたことから、本橋の設計者は多大な労力をかけてねじりまんぽを設計する必要性を感じなかったのではなかろうか。
理者である南海電鉄の案内で本橋を訪問する機会を得た。アーチ部を4層の煉瓦で巻いているが、図3のように、アーチ部の煉瓦の端面がポータル面にそろっていない。これが斜橋であることのひとつの証である。東側ポータル(図4-1)からはあまり感じないが、国道に面する西側ポータル(図4-2)からは水路にやや張り出して通路が設けられ側壁がかなりの高さをもっていることが看取できる。
|
 |
 |
|
図4-1 大師第16号拱渠の東側ポータル |
図4-2 大師第16号拱渠の西側ポータル |
天端の煉瓦には図5の刻印があった。これは、現在の大阪市西成区にあった「津守煉瓦」か、同社の関係者が大阪狭山市で経営していた「大阪煉瓦」のものと思われる。いずれも南海高野線の沿線だ。
なお、管理者によれば、本橋は現状において
|
 |
|
図5 大師第16号拱渠に見られる煉瓦の刻印 |
全く問題なく使用できているということである。
(2)九度山発電所水路橋
在の九度山町は農業が中心であるが、かつては九度山町にもさまざまな産業を興そうという動きがあった。中でも、野口 巳之助と小澤 由三郎は急速に発展を見つつあった電力による紡績業に目をつけ、丹生川の急流を利用して発電しその電力で紡績工場を作れば郷土に就労機会を作れるのではないかと考えた。明治29(1896)年に堰堤を築く許可と紡績会社設立の許可を受けたが、事業は思うように進まず5年で断念せねばならなかった。この失敗を残念に思った野口は、明治40年に再び丹生川の水利使用の許可を受け、こんどは岸和田の寺田 元吉2)の協力を得て「和泉水力電気株式会社」を起こして事業を始めた。赤瀬橋のやや上流で取水し、水路で九度山まで導き、発電所を現在の九度山幼稚園近くの川沿いに設けた。工事は大阪の入江組が請負い、44年4月に竣工した。九度山地区に電灯をつけさらに余剰の電力は山を越えて岸和田に送った。
事業は大正6(1917)年に「南海鉄道」(現在の南海電鉄)に譲渡され、引き続き地域の暮らしに役立ってきた。しかし、昭和28(1953)年の大水害で施設が流出し、再建できないまま幕を閉じた。
の遺物は町内のところどころに今も残るが、注目すべきは大師第16号拱渠のすぐ近くにある水路橋だ。
|
 |
|
図7 九度山発電所水路橋のアーチ部の壁面 |
|
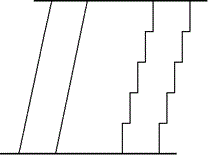 |
|
ねじりまんぽ |
九度山発電所水路橋 |
| 図6 ねじりまんぽと九度山発電所水路橋の壁面の比較 |
太利(ふとり)池から流れ出る小さな水路とそれに沿う通路と約80°の角度で交差している。通常、煉瓦で斜橋を作る時はねじりまんぽという技法を用いるが、本橋は、いわば幅の狭い直橋を少しずつずらして配置することにより斜めに交差しているのである。よって、煉瓦は水平に積まれている。極めて特異な橋梁である。煉瓦のサイズは厚さ約6cm、長手約22.5cm、小口約10.5cmであった。
この構造は、明治時代の土木工学の教科書である「蘭均氏土木学」において、ねじりまんぽに当たる「斜歪穹?」(?は宀に隆)と並んで「有肋斜歪穹?」として紹介されている。が、構造的には目地が縦につながる芋目地が一定間隔で必ずできてしまい、これが弱点となるためねじりまんぽほど優れているとは言い難い。施工面でも、アーチ部の壁面がずれる都度 支保工も動かさないといけないため、優位性はなかったと考えられる。
路橋の天端に上がると、コンクリート張りの水路があった。
|
 |
 |
| 図8 コンクリートで処理された水路 |
|
|
図9 沈砂と水量調節の設備と思われるもの |
コンクリートは漏水を防止するために後年に追加施工されたものと思われる。当該箇所にはコンクリートの壁があって、土砂を堆積させていたようだ。また、スリットの入った煉瓦の壁は、ここに差し込む板の高さを変えて発電所に送る水量を調整していたように見受けられた。煉瓦にはXやYの刻印があった。Xは岸和田煉瓦3)の製造であることを示すものと考えられる。
(参考文献)
|
 |
|
図10 九度山発電所水路橋に見られる煉瓦の刻印 |
1.河村 清春ほか「関西地方の鉄道における「斜架拱」の分布とその技法に関する研究」(土木学会「土木史研究」第10号所収)
2. 小野田 滋ほか「組積造による斜めアーチ構造物の分布とその技法に関する研究」(土木学会「土木史研究」第16号所収)
3. 九度山町史編纂委員会「九度山町史」(昭和40年11月)
1) 根津 嘉一郎(万延元(1860)〜昭和15(1940)年)は、山梨県に生まれて18歳で郡役所の書記となったが、無断で上京して漢学者 馬杉 雲外や古屋 周斎の塾で学んだ。帰郷して家業を手伝いながら政治活動に注力し、村会議員、郡会議員、県議会議員を経て明治37(1897)年から衆議院議員を務めている。政治活動と並行して実業にも力を入れ、38年には赤字が続く東武鉄道の社長に就任して路線延長や東上鉄道との合併など力を発揮した。以後、多くの鉄道の再建に取り組み、鉄道王の異名を取った。
2) 寺田 元吉(安政2(1855)〜昭和6(1931)年)は、江戸時代から続く酒造家の寺田家に生まれ、明治7(1874)年に分家して清酒醸造業を継承するとともに、関西製綱(明治45(1912)年)、東洋麻糸紡織(大正4(1915)年)の設立に大株主として参加し、大正9(1920)年には佐野紡績を株式会社に改組して家業とした。本稿に出てくる和泉水力電気のほか、五十一銀行、泉州織物の経営にも当たっている。実兄
甚与茂(じんよも)、異父弟 利吉とともに寺田財閥を構成し、岸和田の近代化を牽引した。
3) 岸和田煉瓦は、元岸和田藩士である山岡 尹方(ただかた)が明治20(1887)年に設立したものであるが、その前身は士族授産事業として始められた煉瓦製造会社で明治5(1872)年の設立と非常に古く、日本の煉瓦産業の先駆的事業として注目される。共同出資者のひとりに寺田 甚与茂がいる。製品にXの刻印が多いのは山岡がキリスト教信者であったからというのが通説である。なお、岸和田の臨海部には大阪窯業の煉瓦工場もあり、煉瓦の一大産地だった。
|
|
|